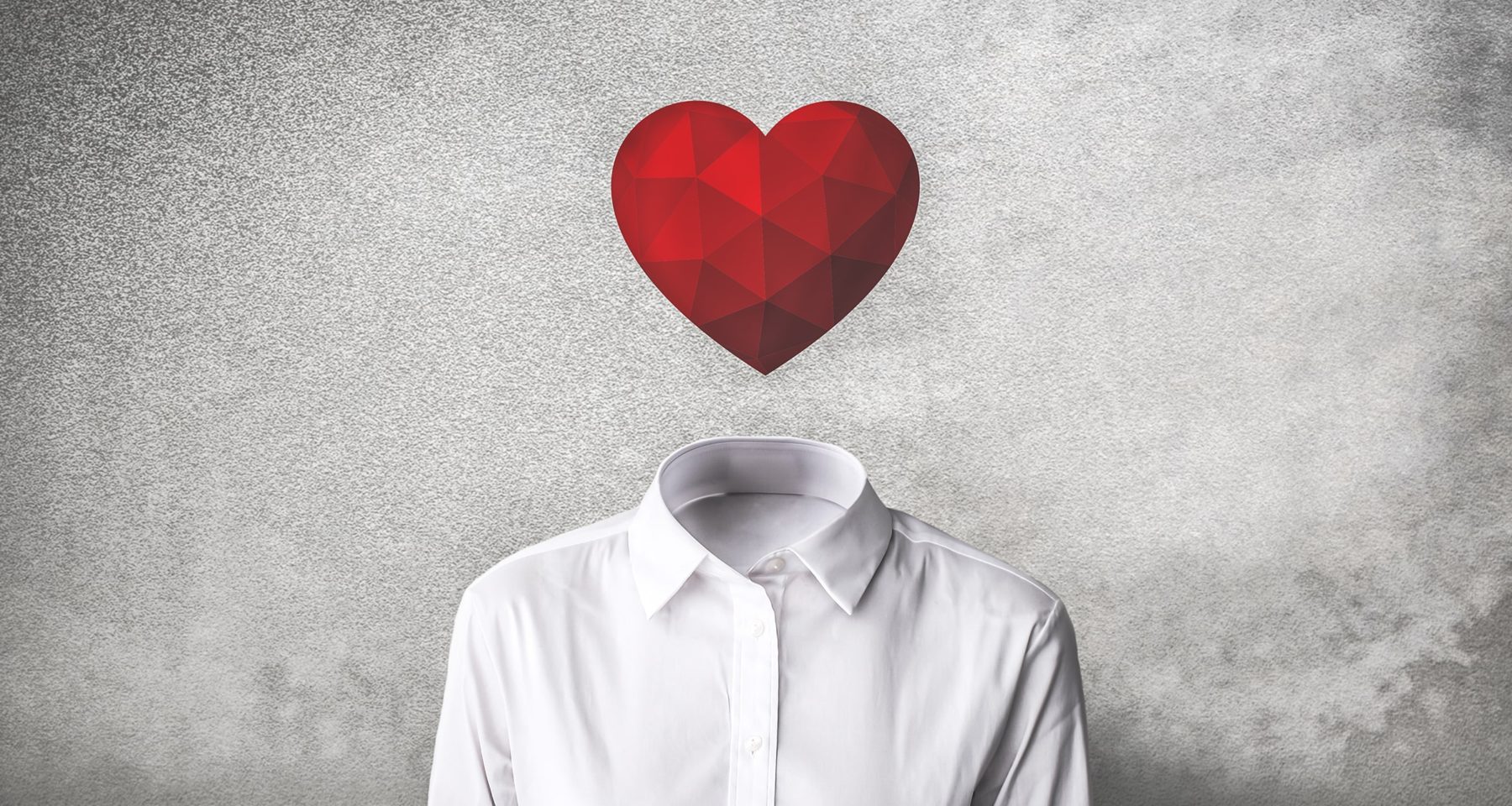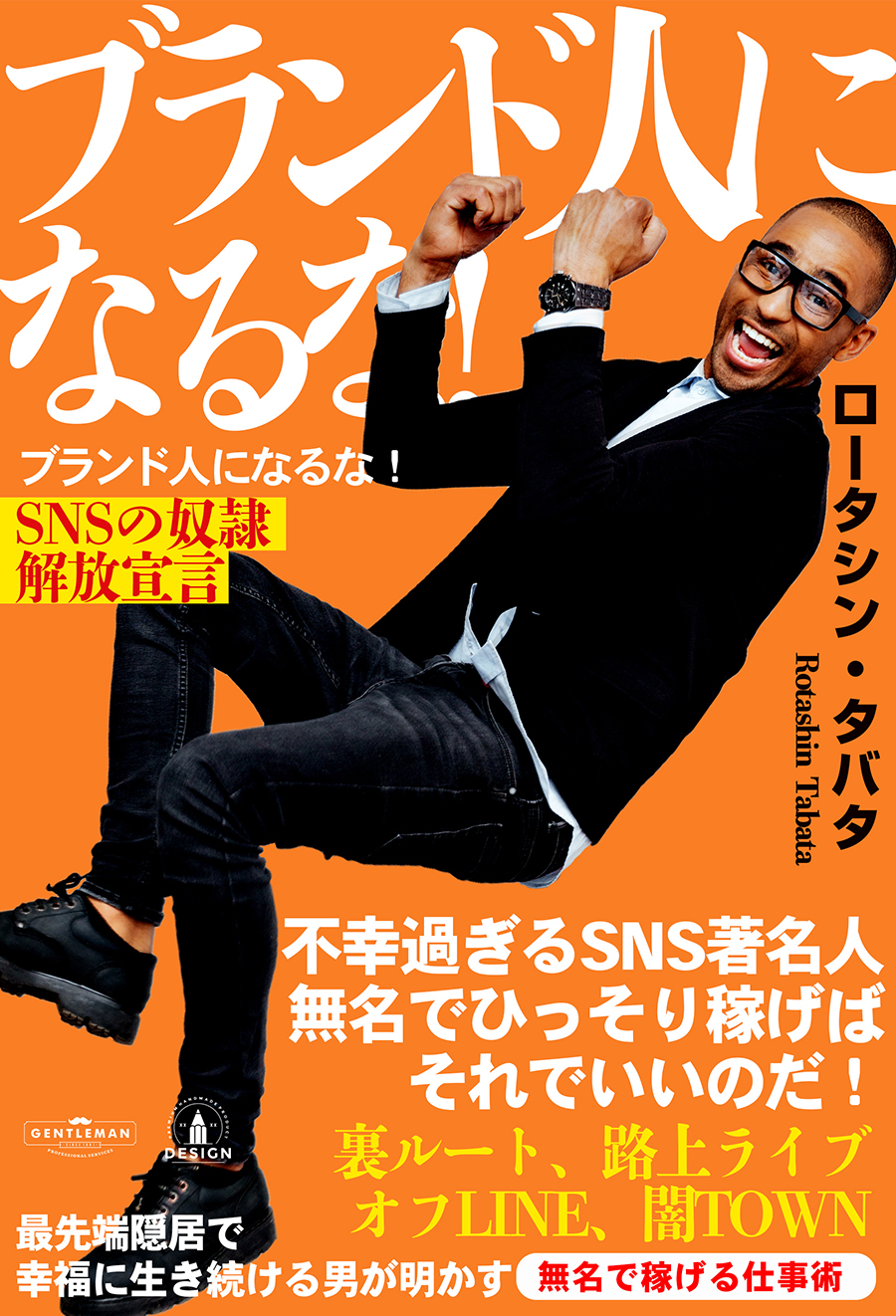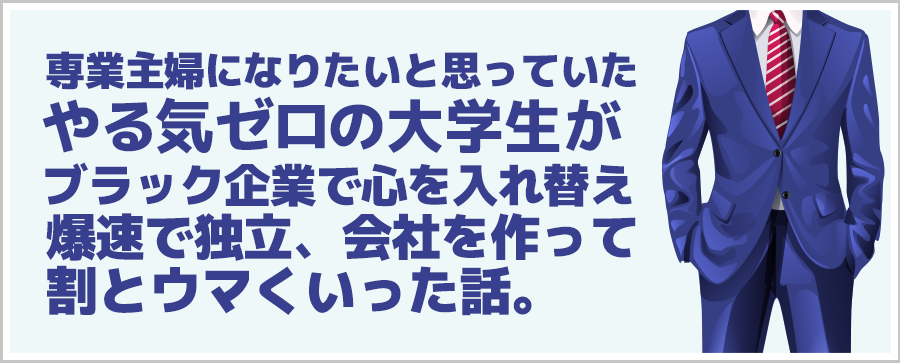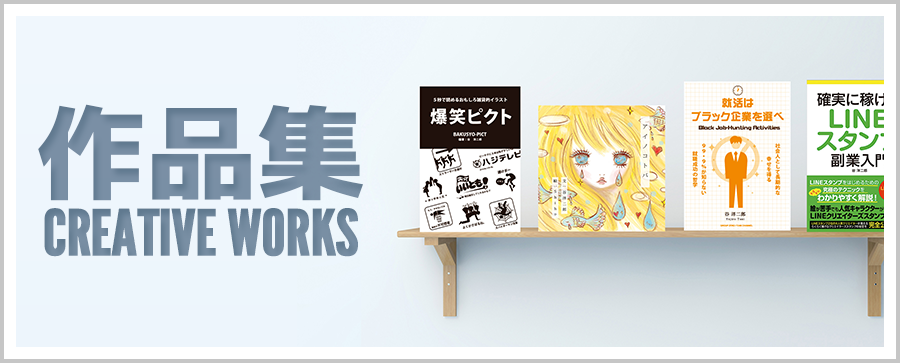社員の生産性を劇的に高めたいなら、働き方を変えるより、昼休みの過ごし方を「ほんの少し」変えるだけで、成果が得られるかもしれません。
100冊以上の成功科学の書籍を読んでいく中で、社員同士が「昼休みを一緒に過ごす」ことが、職場の生産性や創造性を高めるかなり良い施策であることが分かってきました。
そこで、今回は、【昼休みを一緒に過ごす】だけで社員の生産性と創造性は高まる原理や研究を解説し、職場での昼休みの過ごし方を独自に提案していきたいと思います。
本記事の目次
4人のチームで同時に休憩を取ると、受注率が13%向上
一緒に休憩を取るという肉体的シンクロが、仕事に大きな成果をもたらす
株式会社日立製作所フェローの矢野和男がウエアラブルセンサを使って職場の従業員の行動を計測、そのビッグデータを人工知能で解析した画期的な研究の中で、4人のチームで同時に休憩を取ると、受注率が13%も向上することが分かりました。
休憩時間の活発さを向上する施策として、同世代の4人のチームで休憩を同時にとるようにした。その結果、休憩中の活発度が10%以上向上し、さらにその結果、受注率が13%向上した。これにより、休憩中の活発度を変動させることにより、受注率を変動させられることがわかった。
矢野和男 (2018)『データの見えざる手 ウエアラブルセンサが明かす人間・組織・社会の法則』,p.91-94,草思社
また、休憩時間の会話での身体運動が活発ではない日は受注率が低いことが分かっています。矢野和男フェローの研究では、他人と身体的なシンクロを促すことが、生産性や幸福度を引き上げる根源としています。
より良い関係性や気力や体力を土台に、社員同士が一緒に「休息」を取ることで、本業の勢いが増すわけです。
できるだけ一緒に休憩を取るだけで、12億円のコスト削減効果
スキルや性格や能力よりも、一緒に休憩をすることの影響が大きい
マサチューセッツ工科大学のAlex “Sandy” Pentlandが2012年に行った米国銀行コールセンターでの実験では、それまでばらばらにとっていた休憩をメンバーができるだけ合わせてとるという施策により、最大20%も生産性が向上したことが分かりました。
一緒に休憩をとるだけで、銀行全体のコスト削減効果が12億円にもなったのです。この実験で定義された生産性は「電話が掛かってきてから対応終了までの処理時間」でした。
さらに驚くことに、休憩時による生産性のプラスの影響は、スキルや性格や能力などの他の要因をすべて合わせたものより、大きかったということです。
仕事でマニュアルが細かく定められたコールセンターのような仕事の場合、スキルや性格や能力よりも、「いかにその場の仕事に徹するか」で、仕事のパフォーマンスが決まりますよね。
だからこそ、スタッフ同士が一緒に休憩をすることの効果がより明確に出たと言えるでしょう。
オフモードの会話がオンモードの成果を高める
給湯室での会話を奨励する企業は生産性が高い
その他、文献を通して、以下のような研究報告を閲覧することができました。
MITメディアラボの研究員、ベン・ウェイバーによると、「昼食時に大勢とテーブルを囲んでいる者が、実質的に高い業績をあげている社員だとわかった」という。
エリック・バーカー(2017)『残酷過ぎる成功哲学9割がまちがえる「その常識」を科学する』,p.205,飛鳥新社
ギャラップ社の調査によれば、給湯室での会話を奨励する企業は生産性が高いという。
デイビッド・ロック(2019)『最高の脳で働く方法』,p.322,ディスカヴァー・トゥエンティワン
ポイントは、オフモードの時にしっかり喋ることです。オンモードの仕事中にぺちゃくちゃ喋るのではなく、オフモードで喋ることに意味があります。
昼休みを一緒に過ごすと生産性が高まる科学的な理由
理由1:生産性を高める神経伝達物質の分泌が促進されるから
好意的な社員同士が昼休みを一緒に過ごすことは、パフォーマンスを高めるあらゆる脳内の神経伝達物質の分泌を促してくれます。
昼休みを一緒に過ごすことで、プラスの感情にかかわる神経伝達物質「ドーパミン」や「セロトニン」の分泌量を増やし、絆のホルモンといわれる「オキシトシン」や脳内の天然モルヒネとも呼べる「エンドルフィン」が作られます。
昼休みを一緒に過ごすことで、仕事をする際に、ハイモチベーションで集中できる状況を作り出せるのです。
理由2:オキシトシンが信頼関係を増幅させる
人間同士の温かな交流は、幸福ホルモンと呼ばれるオキシトシンの分泌を促します。そして、オキシトシンは、周囲との「信頼感」を構築することにも大きく関わっています。
オキシトシンは信頼も生む。オキシトシンが豊富に分泌されていると、人への信頼感が増すのだ。オキシトシンの増加で人をもっと好きになることもある。オキシトシンは、脳内で恐れや不安を生む偏桃体の活動を抑えるのだ。社会不安障害がやわらぐこともわかっている。私たちがおたがいの感情を理解しやすくなるという働きもある。
デイビッド・ハミルトン(2018)『親切は脳に効く』,p.88,サンマーク出版
昼休みを一緒に過ごせば、お互いのオキシトシンが分泌され、社内の人間同士の信頼関係が高まります。すると、仕事中に特別な会話がなくても、不安をなるべく減らして仕事をすることができます。
単に昼休みを一緒に過ごすということは、脳にとっては思った以上に好影響を与えているのです。
休み時間の社員同士の関わりはデジタル刺激を減らす
一人で休憩を取ると、脳疲労が促進されるリスクが高まる
自分なんかは、個人経営者なので、もう一人の自分と会話(自己対話)しながら、ご飯を楽しく食べることには慣れっこなのですが、ふらっと飲食店に入り、周囲を見渡すと、「スマホ見ながらご飯を食べている」というサラリーマンをよく見かけます。
食事すらマインドフルネスに行動できないとなると、脳はめっちゃ疲れます。デジタル刺激と同時進行する「ながら休憩」は、実質休憩になっていないのです。
一人で休憩を取ると、休憩を暇つぶしに使ってしまいます。身体行動と近接な距離感にあるスマホを扱ってしまいがちです。
一方、休み時間を他の社員と一緒に取ると、他の社員との会話に集中することができ、自然にデジタルデトックスを促すことができます。
そのため、休憩も「休んだ感」が得られ、リフレッシュすることができるのです。
仕事中より休憩中に話すことで創造性は高まる
仕事中の雑談はマルチタスキングを増やし、脳を消耗させる
極論、仕事はシングルタスクで他の邪魔が入らなければ入らないほど、脳を効率よく使うことができます。やりたい作業中に、横から別の力が加わり、作業が中断すると、作業に戻る際に、より大きな脳の力を使わなければいけないからです。
仕事中の雑談が多くなれば多くなるほど、マルチタスキングが増え、脳は消耗させられます。
スタンフォード大学のジェフリ―・フェファーとボブ・サットンはこう述べている。「大規模に行った調査によると、権威のある人たちが職場を歩き回り、従業員に質問を発したり、感想を述べたりするほど、肝心な仕事の創造性は低下する一方だ。なぜなら、創造的な仕事とは本来、挫折や失敗の連続なのに、部下たちは上司の前ではそれができない。すなわち、失敗する心配がなく、創造性が低い仕事ばかりをするようになるからだ。」
エリック・バーカー(2017)『残酷過ぎる成功哲学9割がまちがえる「その常識」を科学する』,p.344,飛鳥新社
特に創造的な仕事においては、「誰から何を言われるわけでもなく、とりあえずチャレンジできる」という風土で、その社員に一点集中させることが大事です。
昼休みを通して多様な人と関わることで、社員の創造性は高まる
多様性のある集団は創造性に富む
昼休みの時間に、職務では関わりのない社員同士が交流する機会を持つと、社内の創造性を高められる可能性があります。
何十年にもわたる社会科学研究で、多様性のある集団はより創造性に富み、よりよい議論ができることがわかっている。コロンビア・ビジネス・スクールのキャサリン・フィリップス教授は、多様性は「新たな情報の視点の模索をうながし、よりよい意思決定と問題解決につなげる」と結論づけた。
モートン・ハンセン(2018)『GREAT@WORK 効率を超える力』,p.249-250,三笠書房
一緒に過ごしながら、多様性を受けいれることで、クリエイティブな仕事の生産性も高まっていくのです。
休憩は集団で、休息は個人で取るのがお勧め
生産性や創造性を高めたいなら、休息と休憩の2つを切り分ける
昼休みを一緒に過ごすことの恩恵は確かに大きいのですが、とは言っても、個人的にゆっくりしたい人は多いでしょう。また、身体や脳のコンディショニングとしての休息を大事にしている社員もいるでしょう。
そこで、お勧めしたいのが、休憩と休息の2種類の休みを設けることです。
昼寝やリラクゼーションなど、本気で疲れを取りたい場合は、個人的に休ませればいいのです。
そう考えると、休むことに対して、柔軟な施策を採ることができる組織で働きたいですよね。
昼休みに様々な社員と過ごしたいという組織を目指すべき
他の社員と「ランチに行きたくない問題」に向き合おう
昼休みを一緒に過ごすことの効果は、会社にとってかなり有益なのですが、前提条件があります。それは、「社内の人間が好意的な関係を築くことに前のめりである」ということです。
会社のランチについて検索ニーズを掘り下げると、否定的な感情を持ったビジネスパーソンが多いようです。
「会社 ランチ 行きたくない」
「お昼 一緒に食べたくない」
「職場 ランチ 抜けた」
「会社 ランチ 一人で食べたい」
「ランチ フェードアウト」
「ランチグループ抜けたい」
「職場 お昼 一人になりたい」
「職場 ランチ 強制」
「ランチハラスメント」
前述したウエアラブルセンサによるビッグデータや脳科学による神経伝達物質の原理からも、肉体行動を共同することは、人間の幸福度を高めます。
ですから、本来、私たちは、社員同士がランチをすることを欲するはずなのですが、逆に、社員同士のランチを避けたいという強い気持ちを持った人も多く存在するのです。
これは、「社員の幸福を実現する」という側面で、組織がぶっ壊れている、組織が機能していないことを意味します。
上司や先輩からランチに誘われて、部下や後輩が「行きたい!」と思う組織と、「うわ、ランチハラスメントやん!」と思う組織では、雲泥の差があると言えるでしょう。
良い組織を作りたいなら、部下や新人ほど、「上司や先輩とランチをしたい!」と思ってもらえるように真剣にコミットすべきなのです。
最後に:組織である強みは、集団行動を取れること
だからこそ、一緒に休むことを突き詰めていこう
以上、【昼休みを一緒に過ごす】だけで社員の生産性と創造性は高まることに言及してきました。
ただし、単に【昼休みを一緒に過ごす】という施策だけを実施しても意味がありません。組織内の人間どうしがお互いをある程度尊重し、好意的に向き合える状況を作る必要があります。
「昼休みを一緒に過ごす」ことの適切なマインドセットが築けている必要があるのです。モテるマインドセットを持っていない人間が、モテるエスコートの上辺の行動だけを実施しても、エスコートされた相手は、まったくエスコートされた気分にならないのと同じです。
組織である強みは、集団行動を取れることです。だからこそ、集団行動をもっと大切にしていきたいですよね。
社員同士が尊重し合い、お互いがお昼を過ごすことができれば、社員同士が相乗効果を発揮し、生産性も創造性も幸福度も業績もグンと高い組織が出来上がるでしょう。
ぜひ、今回の記事も参考にしてみて下さい。
谷洋二郎とは…
10万DL
人気2位
LINE Award
ノミネート
全国グッズ化
森永製菓
ミニストップ
コラボ多数
絵本詩集
ビジネス書等
多ジャンルの
書籍を出版
代表取締役に
個人事務所
一人きりで
日々奮闘中
Web制作
著者
ライター
クリエイター
大学は長崎
熊本を経由し
福岡と東京で
主に活動
2020年2月16日
(END) Thanks for reading!