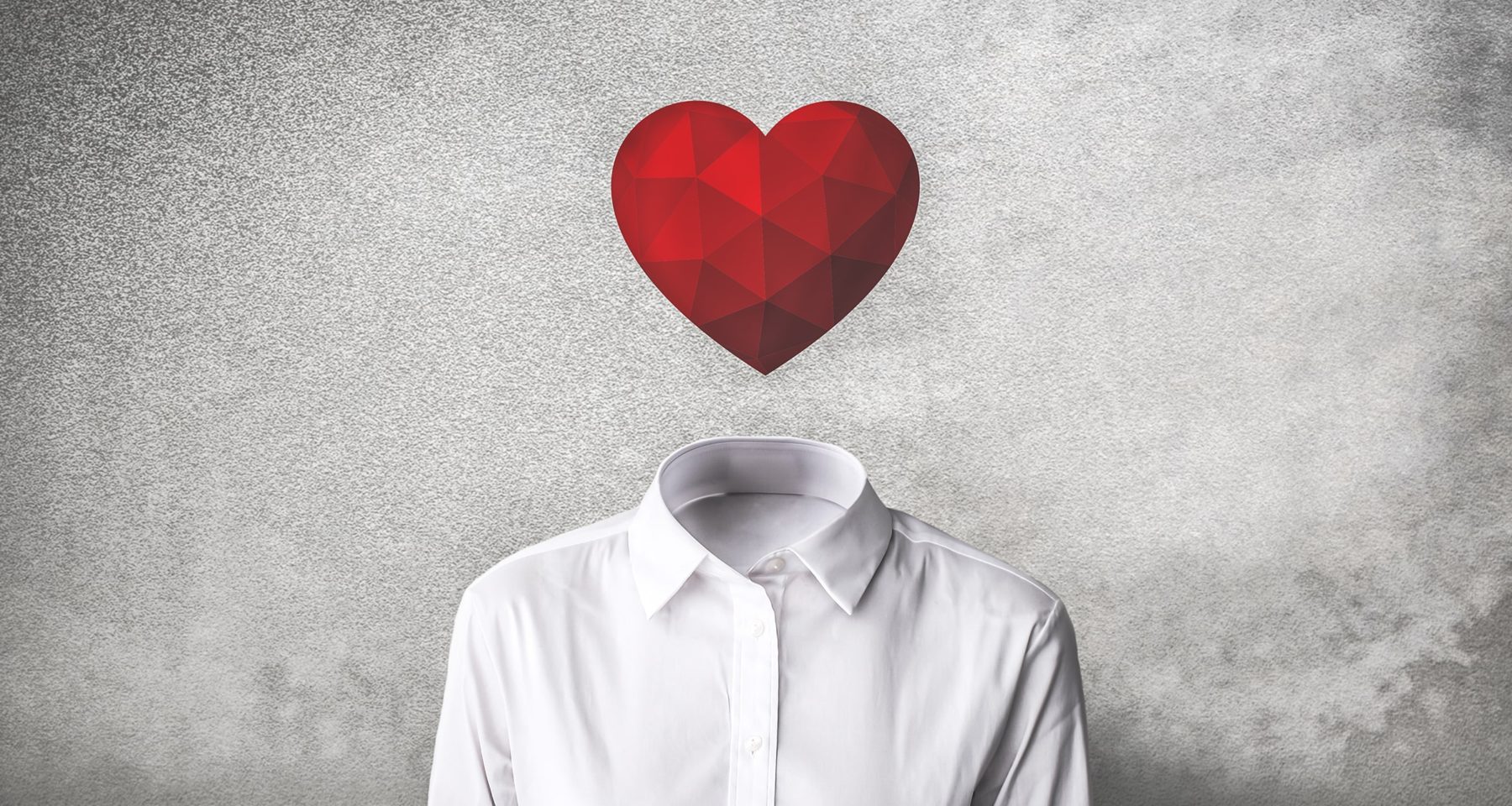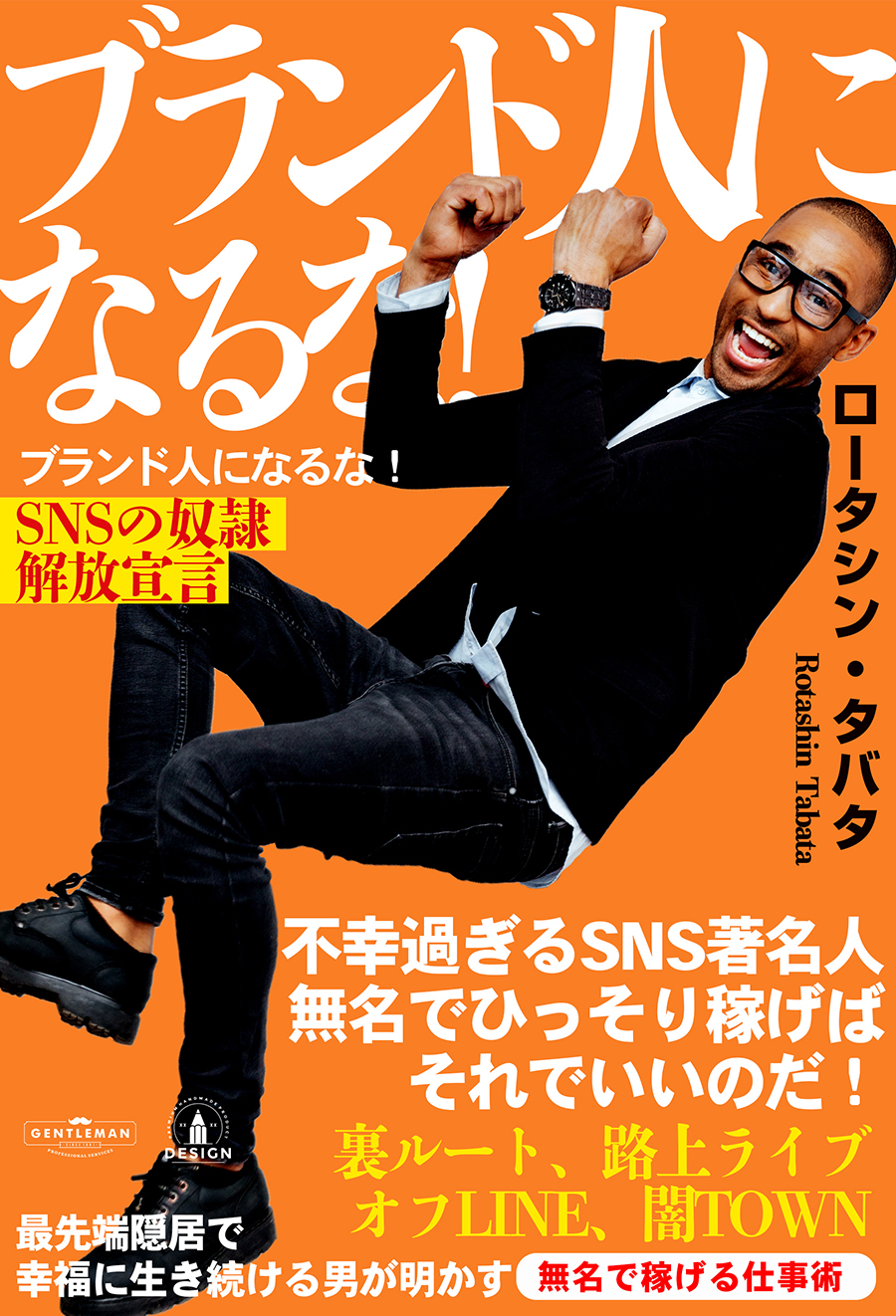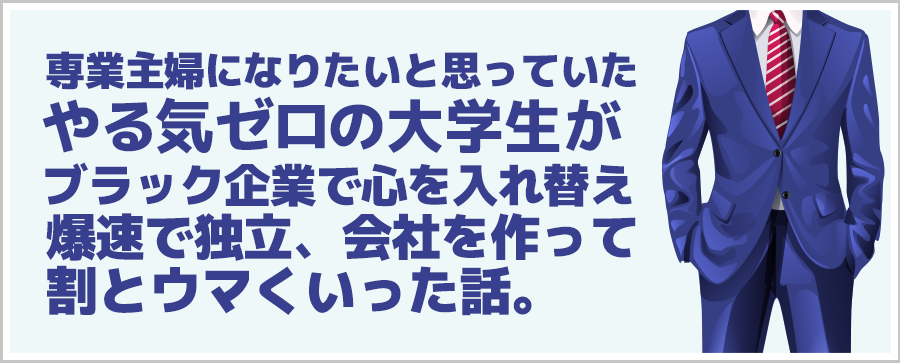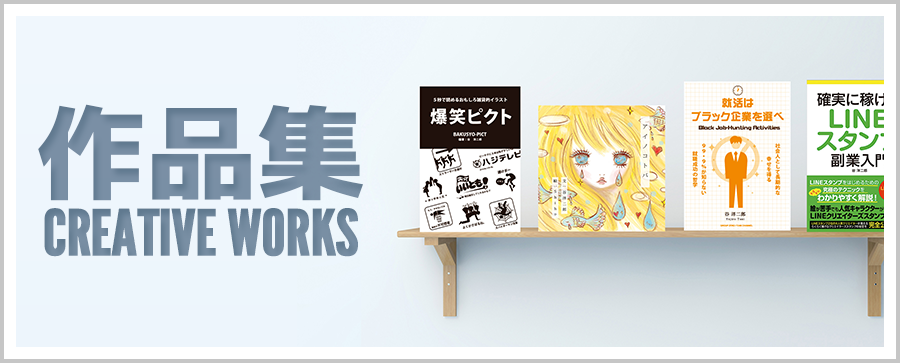友人関係、職場、趣味サークル、交流会、地域コミュニティなど、世の中には「なかなか褒めない人」「めったに人を褒めたいと思わない人」が存在します。
そして、褒めるのが大好きな人でも、ある状況下に置かれると、「褒めない人」「褒めたくない人」に変貌します。むしろ、普段褒めない人が「いきなり褒める」ということも存在します。
さぁ、今回はそんな「褒めない人」にスポットを当て、心理学、脳科学などの観点も交えながら、詳しく解説していきたいと思います。
本記事の目次
人を褒めたくないと思ってしまう理由

褒めることで自分が脅かされるから
単刀直入に言えば、褒めることがダメージになるからです。自分が相手に褒めることによって、自分の自己否定感が募って、精神的ダメージが身体的なダメージにまで波及するからです。
脳科学的に言えば、あなたを褒めることで、コルチゾール値が上がり、心にストレスダメージを与えるからです。ストレスダメージは、ぜんそく、アトピー性皮膚炎、高血圧、心臓病、胃痛、下痢・便秘、腰痛、更年期障害など、身体にも影響を及ぼします。
もしも、褒めることで自己肯定感に傷が入る場合、人は他人を褒めたくないという心理が反射的に働いていくわけです。
褒めない人の特徴:精神的ドケチ

褒めとは心のご馳走である
精神的に褒めることを「ご褒美」しましょう。物理的におごることを「ご馳走」としましょう。
褒めない人は、心をご馳走できない人です
さて、相手におごるには、ある程度の余裕が必要です。余裕がなければ、ご馳走は不可能です。加えて、相手によくおごる人は、「自分がよくおごられてよい恩恵を受けてきた」という経験から、おごることの効用を知り、「自分が余裕がある時は相手におごってあげよう」という認知が出来上がります。
褒めない人は、心の余裕がない精神的ドケチと言えます。
褒めないことがドーパミンを刺激している

褒めない=シャーデンフロイデ
誰かが何かを成し遂げたとき、自分が否定されることが脅威となり、コルチゾール値が高まり、あなたをストレスと見なせば、褒めずにスルーすることが起こります。これは自己防衛的な理由です。
いっぽう、褒めないことを明示することが「快感」になっている人もいます。相手を褒めないことが自分の権威の誇示になり、気分を高めるのです。「相手を褒めないこと」で脳の報酬系が強く刺激されるため、他の行動よりも優先したくなるのです。
褒めないことを自分の報酬にする傾向のある人は、報酬系を刺激する他の出来事が少ない傾向にあります。つまり、心から楽しめるものが少なく、褒めない行動を取ることが「人生のこだわり」になってしまっているのです。
褒めるべく場面で褒めないことは、一種のシャーデンフロイデをもたらします。シャーデンフロイデとは、自分が手を下すことなく他者が不幸、悲しみ、苦しみ、失敗に見舞われたと見聞きした時に生じる、喜び、嬉しさといった快い感情です。「褒めない」とは、褒めるべくことをスルーしているだけなので、「自分が手を下すことなく」相手にダメージを与えていますよね。まさにシャーデンフロイデです。
他人の不幸、褒めないことが、他の物事より激しくドーパミンを分泌させるという体質は切ないですよね。自分のやるべきこと、やりたいこと、主体的なビジョンが人生の中でないとも言えます。
人生は山あり谷あり。完全無欠の幸福を誰も手にしていない以上、「他人の不幸は蜜の味」は全員に通ずることです。しかし、「他人の不幸を味わいたい」という欲求をかき消すほどの、目標、友情、家族、使命などに満たされていれば、他人の不幸でドーパミンを刺激したいなんてことは人生の優先順位になりません。むしろ、軸のある人ほど、どんどん人を褒めることができるようになるでしょう。
褒めない人が持つ単純な厳しさ

褒めない人はレベルの高い相対評価を持ち込む
褒めない人の特徴でしばしば指摘されるのが「相手に求めるレベルが高いから褒めない」というものです。しかし、相手に求めるレベルが高くても、相手を絶対評価で判断し、その尺度を指摘すれば、自然に褒めは発生します。
つまり、「相手に求めるレベルが高い」と思われる人は、レベルの高い相対評価の視点や会話しか相手としてない可能性が高いわけです。「あんまり褒めてくれないよね!」と指摘された際は、相手を絶対評価の尺度で捉え、相手の肯定的な変化を話題に入れていきたいところです。
褒められない人の特徴

褒められやすさは存在するのか
褒められにくい人は確かに存在します。褒めることでコミュニケーソンがポジティブな方向へ広がる予測が立つ場合、行動が「褒める」ことを選びます。他人から褒められずらい人は、周囲の人から「こんなことで褒めても会話がいい感じに広がらないしなー」と思われている可能性があります。
褒められ待機のムードが強い人も、なかなか褒められません。正解があからさまな時、人は、その正解を出すことを躊躇します。あからさま正解に導かれることは、自分がその予定調和に屈しているように感じるからです。褒めてアピールを仕込んでいるのに褒めらないタイプは、アピールの度合いを弱めていきましょう。
返報性の原理から言えば、他人を褒めない人は、人からも褒められない傾向にあります。他人を称える話題を増やしたいところです。
明確な特長を持たずに淡々としている人も、なかなか褒めづらいタイプになります。1つの大きな武器や個性を作り出すだけで、その他のポイントが注目され、褒められやすくなります。
私だけ褒められないという現象が起こる理由

なぜ、集団内で褒めに個人差が出るのか?
ある集団の中で「特定の1人だけが褒められない」という状況が起こるケースがしばしばあります。
いじめが快感になっているいじめっ子と同じ心境
総じて、一人だけを褒めない人間は、自分に余裕がない哀れな人間です。例えば、当の本人だけ群を抜いてダメだったとしても、そのダメさに付け込んで、自分が気持ちよくなるためにいじめを行っている状態なんです。
たった一人を否定することで、自分を表面的に肯定できるからです。でも、それって、薬のようにすぐ消えるんですよ。本当に実力を付けて高めた肯定感じゃないから。だから、薬が切れると、また、その一人だけを褒めないという現象が起きてしまいます。
もし、「私だけ褒められない」ということで悩んでいるのであれば、あなた自身ももっと着実に力を付けて、自分だけが褒められないことに否定感が募らない感覚を手に入れると手っ取り早いです。
普段褒めない人が褒める理由

突発的に褒めを仕込む人
損得勘定で動いている可能性が大きいです。褒めることで相手を取り込みたい理由がそこにあるのかもしれません。
また、褒めたいくらい、その人に対して心が奪われている可能性があります。一般的に親しい人よりも好意レベルが高いと言えるでしょう。
教育的な側面から「褒め」を調整している可能性もあります。要は、あえて普段は褒めないことを軸として動いているわけです。「普段褒めない人が褒める」ことの効用を感じているからこその行動軸と言えます。
褒めるのが苦手な心理

褒めは自己否定感を高める機会にもなるから
人を褒めることができない、褒めるのが苦手な人っていますよね。褒めるのが苦いのは、褒めること(もしくは褒められること)に不慣れだからです。子供の頃から積み上げてきた家庭環境や教育環境が大きく影響しているケースもあります。
褒めるのが苦手な人は、ぶっちゃけ他人にも自分にも興味がありません。野性的な人間というか、人としての哲学が少な過ぎるです。だから、人と接する時に「切り口」が圧倒的に少ない。だから、褒めようにも褒めれない。
成功体験を増やしながら、広い視野、深い思慮、高い自尊心で自分にも他人にも興味を持つことができれば、自然と相手を褒めることが多くなります。
ハイレベルな自分になれば、結局は自分を褒められて、相思相愛になるケースが増えますから、本当に心の余裕がある人は、人をどんどん褒めていきます。
褒めない上司の心理

部下を褒めることができない上司
これまで説明した褒めない人の心理や特徴が単一もしくは複合的に絡んでいます。物事を俯瞰する能力の低い、他人への興味が薄い、といった上司は、部下の出来事や想いを把握できません。褒める以外のコミュニケーションも希薄になっているはずです。
褒めることだけをしない上司は、明らかに「自尊心」が影響しています。部下の成功を見届け、上司は褒めることをする際に、自尊心が低い上司は、「自己否定が反芻する」といったことが起きます。自己否定の反芻をいち早く遮断するためには、「部下の褒めを短くすること」が必要になります。
上司という立場を「権威的」に捉え、部下を褒めることが「権威を落とすこと」だと考える上司もいます。「威張る」「威張っていられること」に価値を感じている上司です。私は、威張らず、最高のエスコートで手を差し伸べ、最大の結果を背中で見せることに価値を置いています。むやみやたらに威張ることは、自分の弱さを露呈しているに過ぎません。
褒めることが部下のモチベーションに繋がらないことを熟知して、あえて褒めない上司も存在します。褒めないことを好転させる上司は、コミュ力が高く、多くの人に慕われているはずです。
褒めない女の心理

褒めない女性とセロトニン
常に勝負している心理があります。日常生活から1つ1つの行動や状況を勝負目線で捉えているのです。
自分の理想がめちゃくちゃ高いところにあって、まだまだそれに自分が到達していないと感じていると、ちょっとしたことじゃ褒めなくなります。
自分のパーソナリティと相手を完全に切り離して、相手に幸せな時間を提供しようというまでには余裕がないんです。だから、まったく勝負が必要ないとこで勝負目線になるわけです。
また、女性は、多幸感を構成する脳内伝達物質であるセロトニンの分泌量が「男性の約半分」かつ「乱れやすい」と言われています。女性は自分の幸せの感覚について、状況によってブレてしまう生き物なのです。
最後に:素直に褒める人の心理

褒めが健全な生命の持続に繋がると腑に落ちている
褒める余裕が出来たこと、人を褒められる自尊心を蓄えたこと、褒めることが腑に落ちる経験をしたこと、それらが身に染みてるから褒めるわけです。
「褒めとけばオッケー」みたいなことも数多く経験してるからこそ、褒めへコミットしている可能性もあります。
相手を褒めることで、相手をなだめ、人間関係を構築していくフローに自分が安心しているから、褒めるということもあります。
自分が褒められるのが好きだから、相手を褒めるというのもあります。これは返報性の原理です。褒められない人の対極で、褒めることでドーパミンレベルが刺激され、分泌が促されるかもしれません。
相手を褒め、相手から褒られることは相思相愛の長期的な結びつきを感じる機会は、多幸感の脳内伝達物質であるセロトニンやオキシトシンの分泌レベルも高めてくれます。
素直に褒める人は、総じて、褒めることが健全かつ快適に生き延びることへつながるとが腑に落ちているのです。
いずれにしても思うのは、素直に褒めることができれば(相手の本質を認めるという意味での)、人生は自分にも相手にも正直で楽しくなります。
住環境や会社の仕組みを始め、いろんなものが人を難しくしてるだけなのかもしれませんね。
谷洋二郎とは…
10万DL
人気2位
LINE Award
ノミネート
全国グッズ化
森永製菓
ミニストップ
コラボ多数
絵本詩集
ビジネス書等
多ジャンルの
書籍を出版
代表取締役に
個人事務所
一人きりで
日々奮闘中
Web制作
著者
ライター
クリエイター
大学は長崎
熊本を経由し
福岡と東京で
主に活動
2019年5月31日
(END) Thanks for reading!